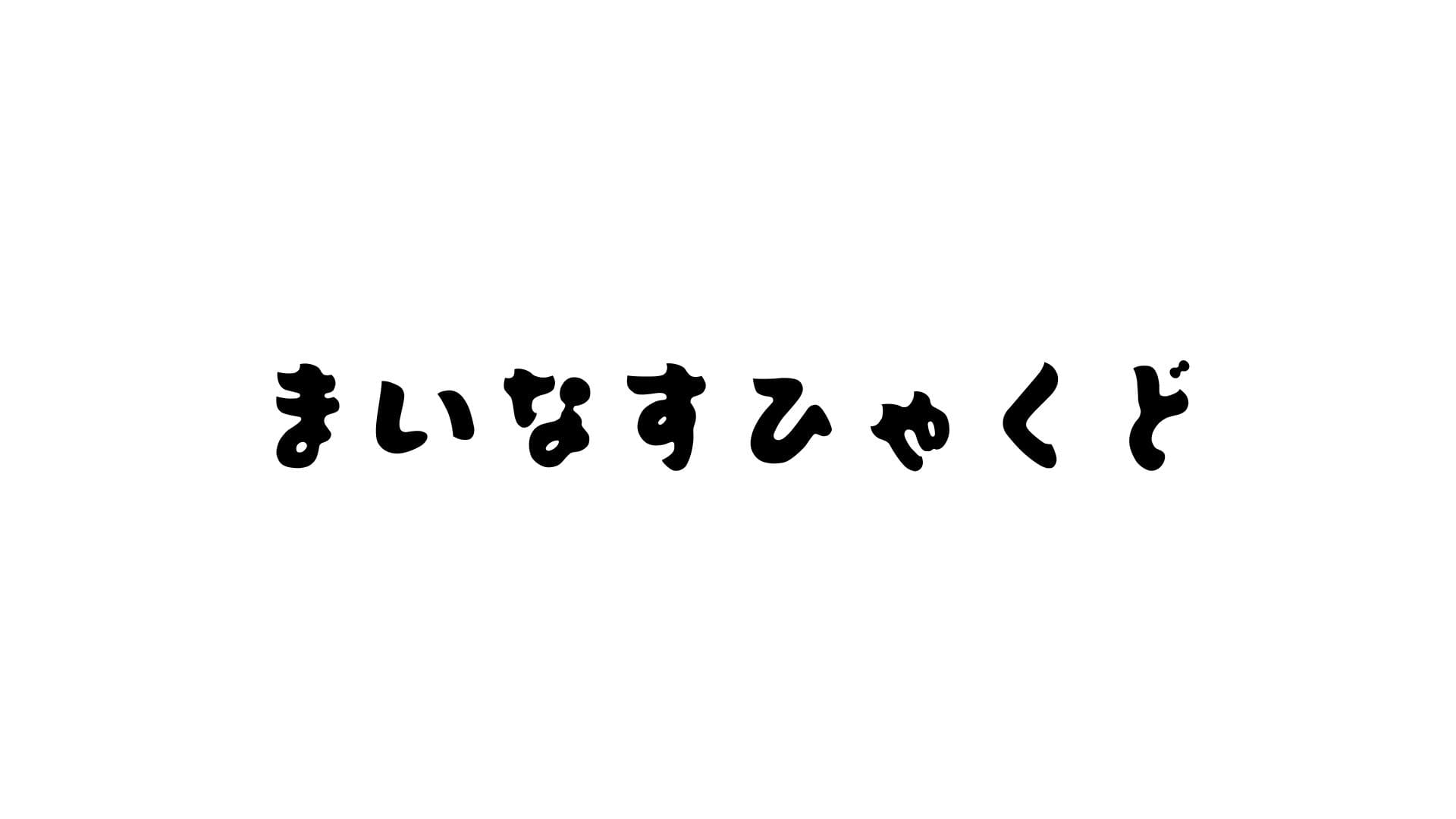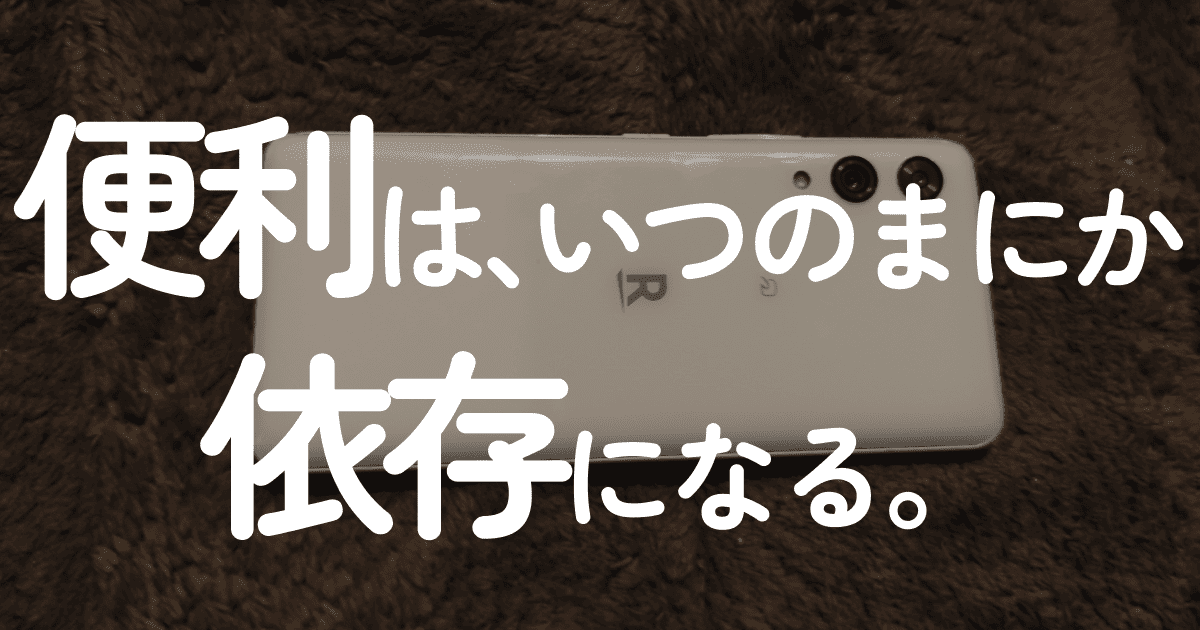こんにちは、ありぺいです。
みなさんスマホ依存患者ですよね?
やめたいですよね、スマホ。
でも「プッシュ通知をオフにする」とか、「スマホ以外の趣味に打ち込む」みたいなあるある対策、正直聞き飽きましたよね?
というわけで今回は、ぼくが普段から意識している「ちょっとしたことだけど、意外と盲点なスマホ依存対策」を3つご紹介します。
スマホ決済をやめてみる
最近、スマホをFeliCa非対応の「POCO F7 Pro」に変えたんです。
そのおかげで、強制的にスマホでのクレジットカード決済やモバイル交通系ICが使えなくなりました。
世間的には、「おサイフケータイが便利!」という声が多いと思います。
でも、決済をスマホで済ませるってことは、それだけスマホに触る回数が増えるってことなんですよね。
はい、スマホ依存の温床。
ぼくが提唱する支払い方法の優先順位はこんな感じ:
- クレジットカード
- スマホ決済(QRコード決済)
- 現金
あ、現金は衛生的に論外です。(口悪)

ぼくは以前、ほとんどの支払いをPayPayで済ませてました。
でもクレカをメインにしたことで、スマホへの執着が一歩減ったんですねこれが。
いや、カバンから財布出すのめんどくさいだろ。
って意見もよくあるけど、冷静に考えて。
それはスマホをポケットに入れてる前提の話。
ぼくはスマホをカバンに入れて生活してるので、スマホも財布も取り出す手間は一緒。
ポケットにチョコ入れてたらみんなすぐ食べちゃうでしょ?

あとは、取り出しやすさという意味では、薄い財布がおすすめ。
ぼくは2019年からOUT OF ORIGINARYというブランドの、超薄型の財布を愛用して使ってます。
そんなちょっとのことでスマホ依存度が変わるわけないだろ。
とも思うかもしれません。
実際、スマホユーザーが1日にスマホを触る平均回数は352回だそうです...
起きている時間で割ると、約3分に1回のペース。
これだけ触ってたら、習慣にならないわけがないんですよね。
じゃあスマホ決済で1日何回あるかって話。
せいぜい多くて3回とかじゃないですかね?
「352分の3を改善したところで、意味ないでしょ」って思う気持ちはよくわかる。
でも、だからあなたはスマホをやめられない。
試しにスマホをポケットじゃなくカバンに入れて生活してみてください。
人生変わります。
モバイル交通系ICカードをやめてみる
次は、交通系ICの話。
ぼくは今は「ICOCAカード」を持ち歩いて、改札ではスマホじゃなくカードでタッチしています。
もちろん、カードが一枚増えるので財布はちょっとかさばります。
でもそのぶん、スマホ依存のストレスを減らせるとすれば、全然アリ。

「スマホで改札タッチ → そのままスマホ見ながら歩く」っていう流れ、習慣になってる人けっこういません?
財布にカードが増えると聞いて、
クレジット一体型の交通系カードもあるじゃん
って思った人もいるかもですが、あれ、相当使いにくいんですよね。
年会費がかかるものが多かったり、地域や提携店舗に縛られたりして汎用性はあんまり高くない。
ビックカメラSuicaとか、イオンSuicaカードとかありますけど、住む環境に左右されすぎるから絶対持ちたくない(笑)
楽天とかPayPayが出してくれたら即買うんですけどね〜。

本は電子書籍じゃなく紙で読む
本ってかさばるし、電子書籍のほうがミニマルじゃない?
もちろん、そう思う人も多いと思います。
でも、ぼくは「なにも持たない」をテーマにYouTube発信もしています。
(YouTubeのリンク)
ぼくの「なにも持たない」の定義は「ムダなモノも思考もなく、人工的なストレスから解放された状態」
モノは少ないけどデジタル依存の人を、エセミニマリストってぼくは呼んでます。(多くの人を敵にまわしそう)

実際、タブレットで本を読んだこともあるんですが、とにかく疲れる。
「目にやさしいモード」なんてあっても、そんなの焼け石に水。
細かい文字をスクリーンで読み続けると、肩はこるしストレスでハゲそうになります。冗談抜きで。
「ストレスで禿げそう」って感覚は比喩でもなく、意外と的を得てたりします。
実際に、長時間のスクリーン使用は眼精疲労 → 血行不良 → 抜け毛の原因にもなるらしいです。
https://www.aga-clinic.com/column/eye-nukege
早い話が、スマホ見すぎるとハゲるってこと。

フサフサを目指して、100万円近くかけて治療してるのに、その努力がスマホごときで台無しになったら、マジで笑えない。
おわりに
というわけで、今回はぼくが実践している「超身近なスマホ依存対策」をご紹介しました。
特別なアプリやタイムロッキングコンテナみたいな高いグッズを買わなくても、日常のちょっとした選択を変えるだけで、スマホとの距離感はちゃんとコントロールできます。
「なんかいいかも」と思ったら、ひとつだけでも試してみてください。
ではまた!