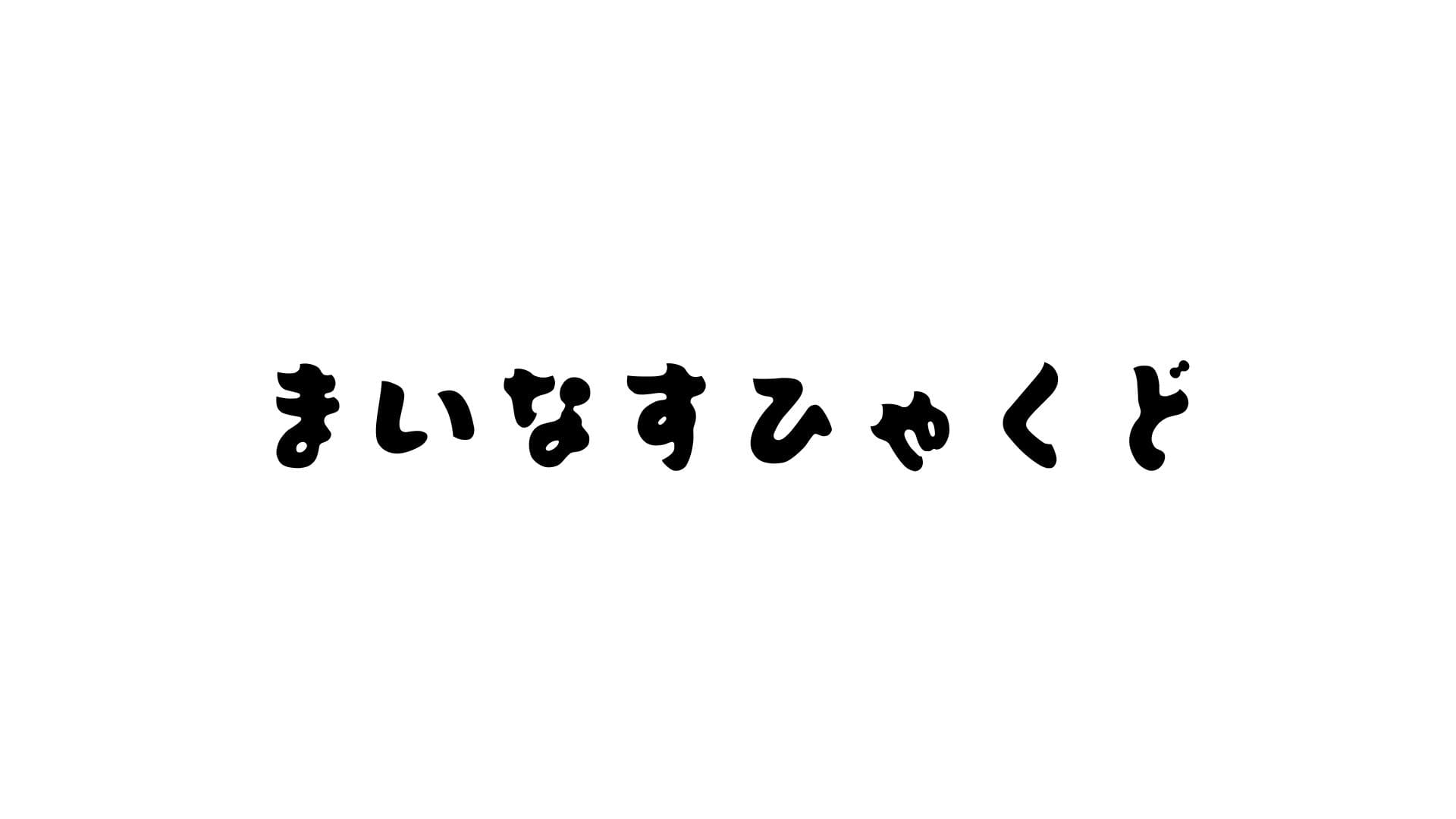こんにちは、ありぺいです。
今回は『2度と挫折しない目標の立て方について』3つの対策を紹介していきます。
2025年も、はや3月が終わって4月になろうとしていますね。
ところでみなさんは、何か今年の目標、立てましたか?
毎年年始になると、来年こそは新しい自分になって頑張ろうって思いますよね。
今年こそは、これを達成したい
っていう目標が、あなたにも一つはあったんじゃないでしょうか?
ですが「今も新年の熱量のまま、日々を過ごせていますか?」って聞かれると、ちょっと疑問ですよね。
多くの人は、新年の目標なんて1ヶ月も経てば忘れてしまいます。
ましてや年末にもなると、「あれ?なんか今年目標たてたけど、全然意識してなかったなぁ」とか「いや、そもそも目標を立てたこと自体を忘れちゃったよ」ってことは往々にしてあると思います。
そこで今回は、年始に立てた「今年こそ…」という目標がなぜかいつもすぐに挫折するんだよなぁ...と悩んでいる方に向けて、
- なぜ目標が挫折するのか
- どうやったら2度と挫折しない目標計画が立てられるか
といった話をしていきたいと思います。
自由だからこそ、ぼくは社会人になってから、目標や予定管理を徹底的に追求するようになりました

一応先に伝えておくんですが、この記事は目標設定の考え方をメインに書いています。
なのでこの手の話でよくある、手帳を使って何かワークを実践していく、みたいなのとは違います。
思考を根本から変えたい人だけ見てもらえたらと思います。
そもそもね、計画を立てようとか、新年の初めとかって、みんな手帳とかノートを買うじゃないですか。
買うとワクワクするというか、一時的にはやる気が出るんですよ。
またね、手帳は数百円とかで安く買えてしまうから、参入障壁が低いわけです。

でも、手帳を1年の最後まで使ったことがあるか?っていう話なんですよ。
多分ないでしょ?

過去のぼくも、何冊も同じような手帳やノートを買っては無駄にしてきました。
手帳がただの紙切れになってしまうのは、かなり勿体無いことだと思います。
目標を挫折する以前の、そもそも目標を立てる段階で挫折してる方は、この記事を最後まで見ると、2度と挫折しない目標が立てられると思います。
記事の構成
前編:そもそも目標を達成するって難しいことなんだよ
後編:【今回のテーマ】2度と挫折しない目標の立て方
多分、皆さんが今までに聞いたことがないような対策も書いているので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。
Contents
そもそも目標を達成するって難しいこと

8%、この数字皆さん何か想像つきますかね。
会社の新人研修みたいな導入になっちゃってアレなんですけど、この数字は、新年に立てた目標を達成する人の割合です。
ピンとこない方もいるかもしれませんが、92%の人が新年の目標を挫折しているって変換すると、そもそも無理ゲーなんだなって理解できますよね。
じゃあ成功する8%とその他92%の違いってなんなのか、ってことなんですけど、
全ては「目標の立て方」なんですよね

もちろん、瑣末な理由は他にもありますよ。
フレッシュスタート効果ってので、人って新年とか月初めなど、行事の節目に異様にモチベーションが高くなる傾向にあるんですよね。
そのおかげで、ばかみたいな高い目標を設定して、失敗に終わるパターン。
もう1個が、計画錯誤っていう、心理学でいう認知バイアスなんですけど、 人って、過去に計画どおりに進まずに失敗した経験が繰り返しあったとしても、新たな計画を立てる際には楽観的な予測をする、っていう傾向があるんですよね。
まぁでも、これらの原因って結局は全部「目標の立て方」で解決するんですよね。
要はモチベーションとか楽観主義とか、そういう人の感情的特性に左右されず動ける、確実性のある目標を立てればいいだけ。
後ほど詳しく話しますが、
曖昧な目標+曖昧な計画、しかしない方ってほんとに多いです。
ですがこれは、
「旅行先を海外って決めて、適当な飛行機に乗ってアメリカに到達しようとしている」
のと同義で、こう聞くと随分馬鹿らしいですよね。
「目標を持ちなさい」っていう努力信仰が日本では強いにも関わらず、「目標の立て方を教えてくれる大人」って世の中少ない。
その影響からか、夢や目標はなんとなくあるのに、そこに至る具体的な過程を上手に描けない人って多いと思います。
2度と挫折しない目標の立て方

前置きが長くなっちゃったんですが、ここからが本題です。
目標を振り返る習慣を持つ
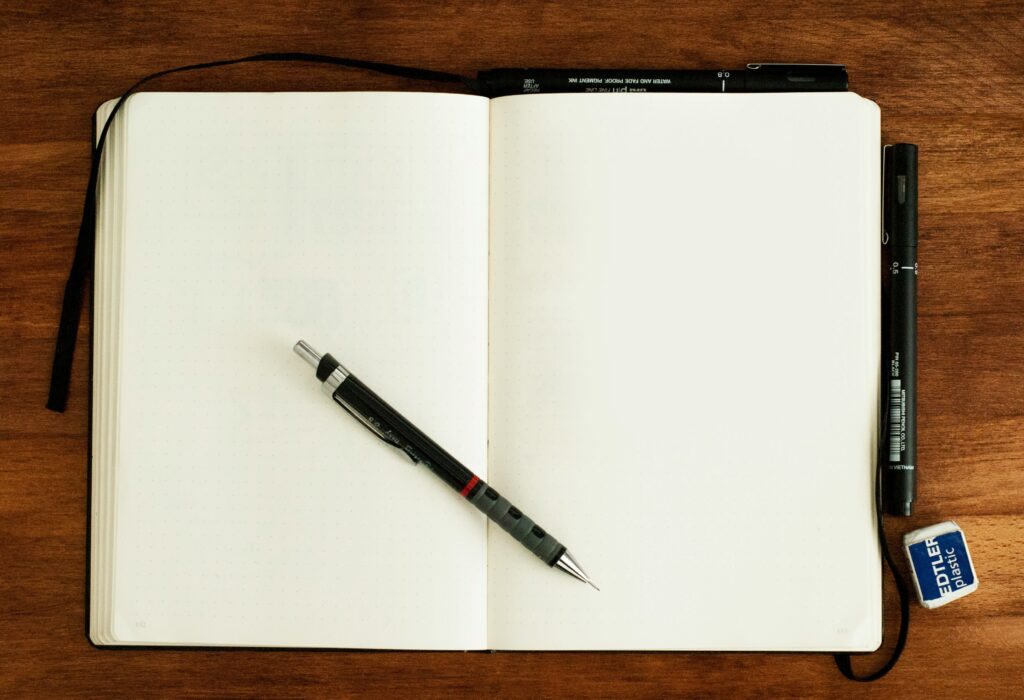
2度と挫折しない目標の立て方、1つ目は、目標を振り返る習慣を持つ、です。
いやいや、自分にとって大事な目標くらい毎日意識できてるし、忘れたりしないよ
って思う方もいるかもしれないです。
が、ここでいう「忘れたり」を、文字通り失念の意味で捉えてはいけません。
正しくは、生活の上での優先順位が下がってしまう状態のことです。
仕事やプライベートが忙しくなると、つい目標より目の前のタスクに追われ、後回しにすることってよくありませんか?
立てた目標も、定期的に振り返らないと忘れてしまって、またいつもの生活に戻っちゃうんですよね...

意識ってばかにならなくて、日頃大事にしてないことって、簡単に気にしなくなってやめちゃいますよね。
目標って、一回立てたらそれで終わり、みたいなイメージがあるんですが、週や日毎に振り返るっていう習慣がないと結局続かないです。
ギターの基礎練習を1日にこれだけ頑張るとか、目標のための行動を習慣にする人は多いんですが、目標を振り返るっていうのを習慣にしてる人ってかなり少ないと思います。
ここで注意したいポイントがあります。
そもそも、どの手帳やノートに目標を書いてあったけ、っていう状態は、目標を立てる以前の問題なので絶対に避けましょう。
大事なのは、目標を振り返る手間を極限まで軽くするってこと。
「20秒ルール」という心理用語があります。
良い習慣を増やしたいときは、その行動をするのにかかる手間を20秒だけ減らす。
ハーバード大学 ショーン・エイカー著『幸福優位7つの法則』
ただノートや手帳の在処を数秒探すだけだろ
って思いがちなんですけどね。
いい意味でも悪い意味でも、習慣の定着には「いかに楽できるか」が要因なんです。
電子or紙のどちらかに統一

そこでまず、目標管理を電子か紙の手帳か、どっちかに統一しましょう。
電子か紙でまとめるか、っていうのは永遠の課題です。
が、結論から言うと、どちらにもメリット・デメリットはあるので、自分のやりやすい方で大丈夫です。
ちなみにぼくは、普段は紙で思考しメモして、最終的にはPCにまとめてます。
理由は字が汚いのと、PCの方が検索しやすいからです。(20秒ルール)

ここでそれぞれの注意点を述べます。
電子の注意点
まず電子なら、目標管理に使うアプリを一つに絞りましょう。
今やNotion、TickTick、GoodNotes...調べれば管理ツールなんて無限に出てくるんですが。
おすすめなのは、1個のアプリで目標設定、タスク管理、日々のTODO、まで一括して行えるものが理想です。
ぼくはエクセルにシートごとに分けて管理してます。
理由は、アプリのように広告や複雑な機能がないからです。

ここで大事なのは、機能を活用することに気負いすぎないこと。
今のアプリってマルチタスクができて便利なので、ついつい効率重視で色々機能を覚えたくなります。
その気持ちは痛いほどわかります。
ですが、冷静に考えてください。
目標設定って結局は、手段でしかないです。
アプリに詳しくなったところで、行動しなければ本末転倒ですよね。
なので基本的にアプリは「自分に馴染みのあるもの」か「多機能なんだけどUIがシンプルなもの」にしましょう。
迷ったらエクセルかスプレッドシート一択!

紙の注意点
次に、紙の手帳の場合は、これも1冊にまとめましょう。
ウィッシュリストとか、やりたいことリストとか、分けて手帳やノートにまとめてないですか?
分けて保管するほど、情報の管理が複雑になります。
例えばデスクトップにフォルダが何十個もある人は、視覚的ストレスが増え、必要なものを見つけるために余計な時間を取られます。
一冊にまとめちゃいましょう。
ちょっと分厚くなるかもですが、持ち運ぶ頻度が少ないなら問題ないです。
そもそも外出時は紙のメモ一枚だけ持ち歩き、家に帰って気づきをノートにまとめるのがミニマルでおすすめ。
ちなみにノートは小さくて厚いよりも、大きくて薄いものを選ぶのがコツ。
思考の幅は書く紙の大きさに比例する、っていうのをゼロ秒思考の本で見たことがあります。
科学的にどうかはわからないんですが、目標を書くときって、やっぱり大きく考えたいじゃないですか。
「自分にはちょっと厳しいかもな、でも頑張ったらいけそう」っていうのを多くの人は目標にすると思うので。
あとは、字が小さすぎるとシンプルに振り返るとき大変。
なので、やはり大きめのサイズの手帳がおすすめです。

目標計画を具体的にする

2度と挫折しない目標の立て方、2つ目は、目標計画を具体的にする、です。
改めて、目標計画が曖昧な人って、世の中めちゃくちゃ多いです。
以前はぼくも「やることをなんとなく決めて、あとは実践するのみ」とか「計画に時間かけるより行動が大事」って思ってた時期があったんですけど...
今振り返ってみると、そのマインドでは大した成果は出なかったです。
もちろん「考えるより動け」っていうのは自己啓発でも口酸っぱく言われています。
現代って情報過多なので、頭でっかち民が増えて行動しない人が多いからこそ、とりあえずやってみよう精神が大事なのもわかるんです。
ただ、その気持ちが先行しすぎるのは、ちょっと危険な文化かなと個人的には思ってます。
人って、曖昧なもの、やるべきタスクが決まっていないものに対して、モチベーションが低くなる傾向にあるんですよね。
例えば「1年以内にギターで一曲弾けるようになる」っていう目標を決めたとします。
これだけを指針に行動したとすると、1年後どういう状態になっているでしょうか。
もし1曲弾けるようになったとしても「え、このクオリティでいいのかな」とか「これはギター上手くなったのかな」って絶対自分に対して疑心暗鬼になっちゃうと思うんですよね。
指針が曖昧→達成感が得られない→行動欲が徐々に落ちる
徹底した目標計画の細分化

そこで、徹底した目標計画の細分化です。
年間目標を決めたら、月毎に何をやるか、次に週ごと、最後は毎日のTODOにまでやるべき行動を現実レベルに落としていきましょう。
先ほどのギターの例だと
1年以内にギターで1曲弾ける
↑
1月はCのダイアトニックコードを何も見ず弾けるようにする
↑
1月の1週目はCのダイアトニックコードの各ポジションを覚える
↑
1月3日はFコードを全ての弦が鳴るように押さえて弾く
みたいな感じで設定します。もうひたすら逆算ですよね。
毎日のTODOまで考えたら、やるべきことがめちゃくちゃ明確になりましたね。

ここで大事なのが、目標設定は完璧じゃなく、最大化を目指そうってこと。
ギターのダイアトニックコードって何種類あるんだろう?
それらを全部網羅するには、毎月どう時間配分したら...
なんて難しく考える必要ないです。もう少し肩の力を抜きましょう。
完璧にやろうとしがちですが、大事なのは必要なタスクを見極めることです。
やろうと思えば上限なんて無限に設定できます。
でも人生の時間は限られているのと、目標をガチガチに固めたところで先のことなんて誰にもわかりません。
目標設定に時間をかけるより、毎日やるべきタスクが決まったら見切り発車でいいので動くこと。
まずは毎日ギター触ることから。
馬鹿馬鹿しく聞こえますが大丈夫。それすら続かない人が世の中9割。

ぼくも以前はブログのデザインとか変にこだわってた時期がありました。
結果、トップページだけそれっぽく作って記事投稿をろくにせず、挫折した過去があります。
そこから学んだのが、本質を見誤る危険性。
ブログで大事なのは、デザインより記事の質と量。
見栄えだけ良くても中身スカスカだと、見なかったらよかったって思いますよね。
でも逆に、見栄え雑でも中身が良かったらお得感があります。
考えることから脱出して行動してる時点で、あなたは他の人より優位に立ってます。
仮に1年後に目標達成できなかったとしても、全然問題ないです。
まず目標に対してどれくらい自分は動けたのか、できなかったか、を評価できます。
さらに数字という客観的視点で認識することで、来年の新たな目標に繋げていくこともできますよね。
「1月は腕立て伏せを連続して平均50回ほど毎日続けれた」よりも「1月3日は腕立て連続50回できた、1月3日は腕立て連続52回できた」の方が、成長を実感できるのは明白です。
程よく完璧主義になってみる
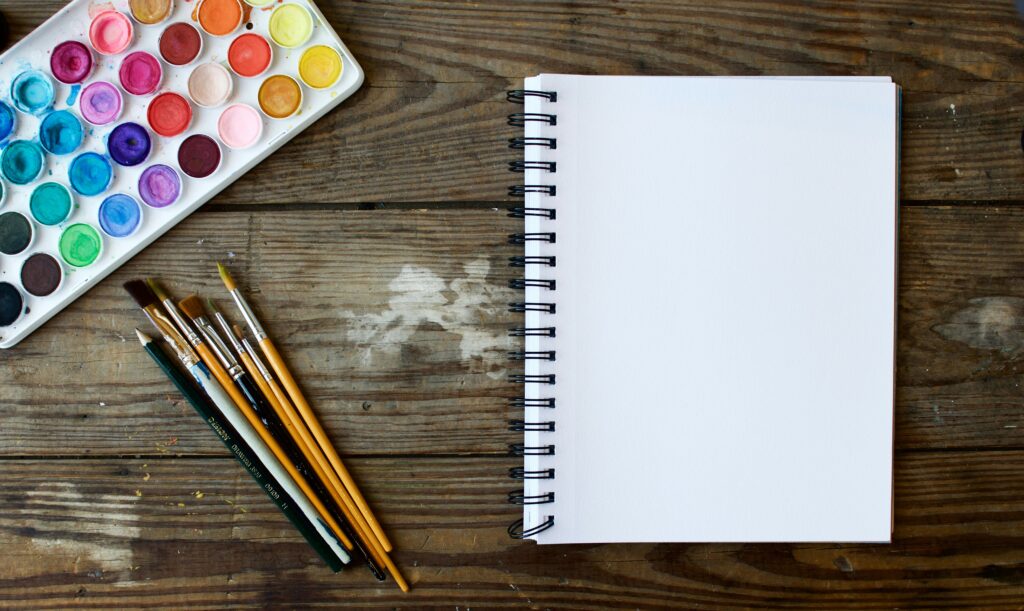
最後に、2度と挫折しない目標の立て方、3つ目なんですが、程よく完璧主義になってみるっていうことです。
これに関しては補足というか、でも、実はここからが超重要なんです。
目標を達成できない人の本質的なマインドについて、ちょっとぼくなりに思うことがあってですね

目標を達成できる人とそうじゃない人の間にはさまざまな要因があると思うんですが、自分のやっていることに対するこだわりが低いっていうのが、かなり大きな要因を占めているんじゃないかって感じます。
こだわりが低いって、なんかさっきから抽象的なんだよ
って、思われるかもしれませんが、全ての面において(今みたいな回答も含めて)そう感じるんですよね。笑
例えば、10のクオリティのものを作るとします。
目標を達成できる人が「10」努力をしているなら、目標を達成できない人って「1」努力して張り合っているんですよね。
当然結果は違ってくるわけですが、ここで重要なポイントがあります。それは...
目標を達成できない人って、「1」努力をしたら「10」のクオリティのものを作れるって本気で信じているっていうことです。(ここテストでますってくらい重要)
いやいや、そんなばかな夢物語持ってないよ
って思うかもしれません。
では質問します。
じゃあ今、目標に向けて具体的に何かやってる?

って聞くと結構な確率で、1日のうち目標に対してやっていることの種類や時間が驚くほど少なかったりします。
またはちゃんと行動や成果を言葉で記録してないからこそ、とても抽象的な答えが返ってきます。
さらにタチが悪いのは、やった気になっている人。
音楽聴きながらだと集中できる、みたいなね。(実際は生産性落ちてます)

でも、本人にとってはそれが普通というか、「自分はその程度で限界」だと思っている節があるんですよね。
別に努力できるから偉いってわけでもないんですが。
努力量の定義や物事に対する認識が、両者の間でそもそも全然違うよねっていう話です。
楽観的すぎるのも良くない

そこでぼくからの提案なんですが、程よく完璧主義になってみるっていうのをおすすめします。
完璧主義って悪い意味で使われがちなんですが、目標達成できないとか、ついつい怠けてしまう人って、総じて楽観傾向が強すぎるんです。
でも、それが悪いとかじゃないんですね。
大体、人って本来物事をルーズに考えるように設計されてるので、むしろこの状態がデフォルト。
例えば、夏休みの宿題なんかその典型例。
宿題の量からして「これなら10日で終わらせれる」っていう当初の予測は、秋の始業式3日前に必死になって机に齧り付く姿勢によって脆くも崩れ去っているわけです。
会社員なら、いつも家を出る時間の見積もりが甘くて、電車にギリギリで駆け込むみたいな。
これは、頭がいいとか悪いとかの話ではないです。
優秀な人でも認知バイアスの罠にあっさりハマります。
むしろ優秀な人ほどプライドが強いので、案外抜け出しにくかったりします。
特に計画に際しては楽観主義になる人が多いと思うので、完璧主義を目指すくらいの気合で、ちょうどいいんじゃないかなって思います。
朝8時~9時は胸の筋トレ(Youtube動画を手本に、25分×2セット)、インターバルは5分、その5分間は瞑想に充てる
みたいな感じで、誰にでも具体的に説明できるぐらい詳細に決めておくのがいいと思います。
結局1の努力しかできない人って、1の計画しか立てていなかったりするんですよね。
10の努力を可能にするには、10の計画を立てる必要がある、っていうのをここでは伝えたかったんです。
さいごに
というわけで今回は、【2025年版】ということで、2度と挫折しない目標の立て方を3つお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。
記事のまとめ
- 目標を振り返る習慣を持つ
- 目標計画を具体的にする
- ほどよく完璧主義になれ
こうやって言葉にすると単純なんですが、実際の行動に移すとなると、やっぱりそれなりに努力は必要ですよね。
ただ、結局行動って思考からしか生まれないので、その最初の一歩である考え方を中心に、今回お伝えさせていただきました。

年明けに今年の目標を設定された方も、改めて自分の目標なり計画を見返してみて、
本当にこのプランで実現可能かどうか?
っていう判断をしてみてくだい。
それではまた、次の記事でお会いしましょう!