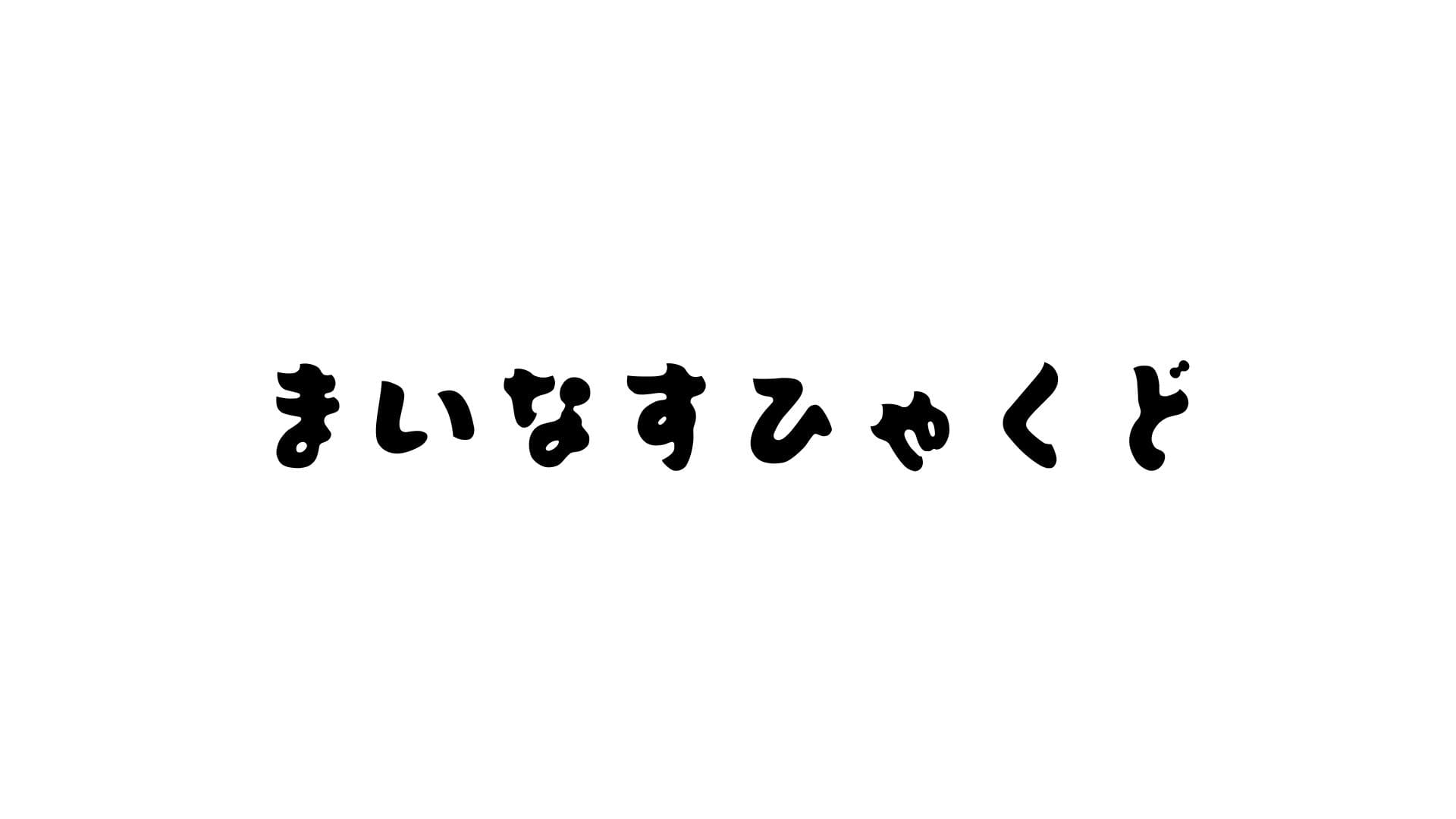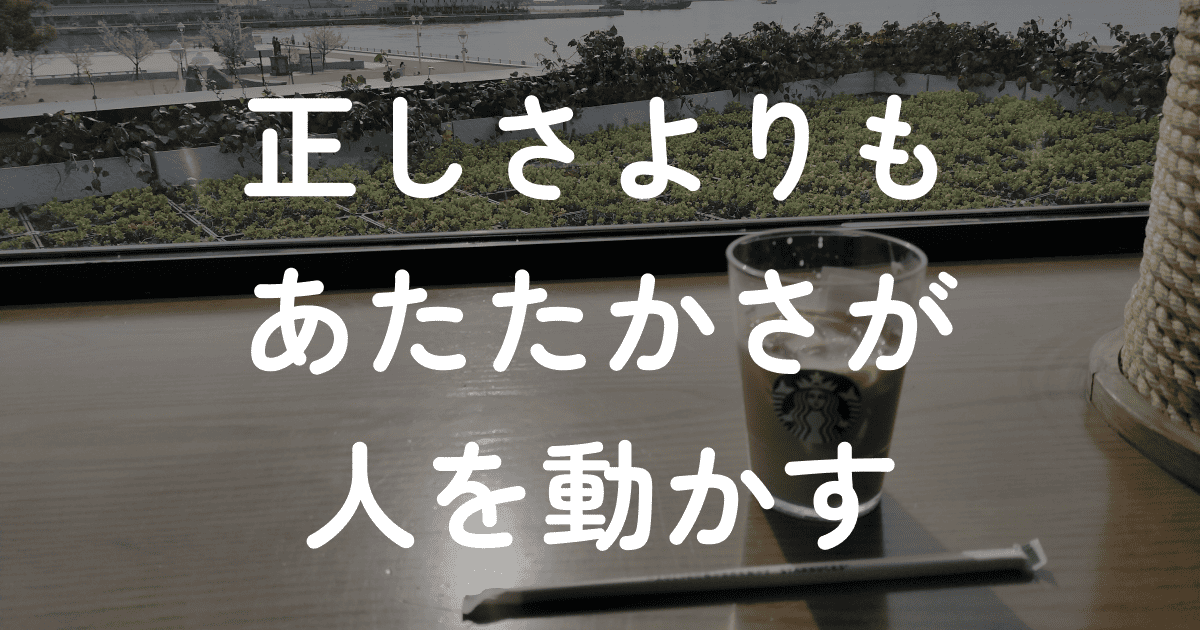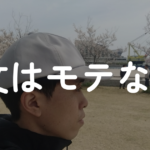人ってやっぱり、人に動かされるんだよなぁ〜と感じた話。
4月の初め。桜が咲き始めた、まだちょっと肌寒い日のこと。
その日、神戸で初めて入ったスタバで、大学生くらいの女性店員さんが注文を取ってくれた。
ぼくはいつも通り、アイスコーヒーのSを頼むつもりだったんだけど、不動産屋さんの引っ越しキャンペーンでもらった500円分のスタバクーポンがあったのを思い出した。
なので、ちょっといつもと違うものを飲んでみよう、ってなった。
メニューの左上にあったスタバのラテに目が入って、

どれかにしようかなぁと考えつつ、店員さんに
どれがおすすめですか?

って聞いてみた。
すると店員さんは、
ソイはさっぱりしてて飲みやすいですね。あとの2つは…まぁ、正直、好みですかね(笑)
って、愛想よく答えてくれた。
でも、その回答にぼくはなんとなく物足りなさを感じてしまって、
お姉さんだったら、どれ選びます?

って追求してみたら、
うーん、わたし個人的には、ソイがいちばん好きですね。
その瞬間、
じゃあ、ソイで。

一瞬で決まっちゃった。
よくよく考えてみれば、不思議なのかも。
商品の一般的な違いを説明されても決めきれなかったのに、「わたし個人的には〜〇〇ですね」っていう、そこに何かちゃんとした論理や根拠があるわけでもない言葉に、なぜか動かされた。
なんてことないやり取りに思えるけど、なんか人を動かす言葉の本質について学ばされた気がする。
AIで何でも調べられる時代。情報もレビューも山ほどある時代。
だからこそ、こういう“その人の意見”に触れて、余計あたたかさを感じたんだと思う。
最近は「こういうデータがあるから」「〇〇さんが言ってたから」って、自分の言葉よりも他人の言葉を借りる場面が増えてる気がする。
あとは、統計なんかを信じすぎて、多数派の意見=正しい、少数派=信用できない、みたいな空気もある。
ぼくは「わたしはこう思う」って、素直に言える人が少なくなってきた気がする。
それって、ちょっと寂しくない?

前回の記事でも書いたけど、正しいだけじゃ本当の意味で伝わらないって思ってる。
どれだけ機械のように正確な答えを説明されたとしても、それは「理解した」で終わってしまう。ただそれだけ。
心が動くわけじゃない。
情情報が溢れる時代になって、ぼくらは“正しい判断”をすることに慣れすぎてしまった気がする。
ネットで調べればすぐに「最適解」が出てくるからこそ、自分の考えにどんどん自信が持てなくなっている。
違うんよ。
正しいかどうかは本質じゃない。「わたしはこう思う」って主張に(無意識に)みんな触れたがってる。
だからこそ、もっと、自分の考えっていうオリジナルな視点と向き合ったほうがいい。
地に足つけて、「ゼロか1か」じゃない人間味を体現して生きる。
そんなスタンスが、これからは大事になってくる気がする。
今度スタバに行ったら、ガチでこう言って注文してみようかなって思ってる。
「ぼくに合いそうなコーヒーって、どれだと思いますか?」
店員さんからなんて返ってくるか、それを考えるだけで結構ワクワクする。
チャットGPTの回答を待つより、何千倍も楽しみで仕方ない。